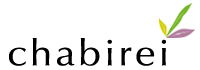お茶の歴史
| 茶がいつ日本に伝わったのかははっきりしていない。茶は薬用として禅宗の修行に用いられていることから僧侶が関わっているとみられる。 かつては栄西によってもたらされたのが最初と考えられていたが、最近の研究によればすでに奈良朝の頃伝来していた可能性が強い。ただし古代に伝わった茶は纏茶(てんちゃ)であったと考えられる。 |

|
『日本後紀』では、弘仁6年(815年)の嵯峨天皇の近江行幸の際、唐から帰朝した梵釈寺(滋賀県大津市)の僧永忠が茶を煎じて献上したと記されている。だが、平安時代に入って文化が、純和風に変わりつつあったと同時に、茶も次第に廃れていった。茶の栽培は栄西が中国から茶の苗木を持ち帰ったのが最初と考えられていたが(そこから日本に喫茶の習慣を広めたとされた)、空海(806年に唐から種子を持ち帰り製法を伝えた)や最澄も持ち帰り栽培したという記録がある。
当初は薬としての用法が主であった(戦場で、現在の何倍も濃い濃度の抹茶を飲んで眠気を覚ましていた、等)が、栽培が普及すると共に嗜好品として、再び飲まれるようになった。一時(貴族社会の平安時代の遊びとして)中国のように闘茶が行われることもあったが、日本茶道の祖・南浦紹明により、中国より茶道具などど共に当時、径山寺などで盛んに行われていた茶会などの作法が伝わり、次第に場の華やかさより主人と客の精神的交流を重視した独自の茶の湯へと発展した。
当初は武士など支配階級で行われた茶の湯だが、江戸時代に入ると庶民にも広がりをみせるようになる。煎茶が広く飲まれるようになったのもこの時期である。茶の湯は明治時代に茶道と改称され、ついには女性の礼儀作法の嗜みとなるまでに一般化した。
茶は江戸時代前期では贅沢品として、慶安御触書でも戒められていたが、やがて有利な現金作物として生産が増えて大いに普及した。生産者にとっては現金収入となる一方で、金肥といわれた干鰯や油粕のような高窒素肥料を購入しなければならなかったので、生産地では農村への貨幣経済浸透を促した。
明治時代になって西洋文明が入ってくると、コーヒーと共に紅茶が持込まれて徐々に普及していくこととなる。昭和期に芸能マスコミの話題(ピンク・レディーが「減量のためにウーロン茶を飲んでいる」と言ったこと)からウーロン茶が注目を集め、缶入りウーロン茶が発売されると一般的な飲み物として定着した。
また、この流行のため中国では半発酵茶が主であるかのようなイメージが広がった。缶入りウーロン茶の好評を受けて飲料メーカーは缶・ペットボトル入りの紅茶・日本茶を開発し、ひとつの市場を形成するに至った。その一方で堅苦しい礼儀作法が敬遠される傾向が強まり、茶道は一般的な嗜みから、趣味人の芸道としての存在に回帰しつつある。